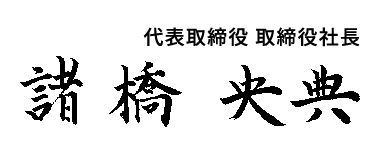現中計の成果と課題、そして2026–28年度中期経営計画への繋がり
2023–25年度中期経営計画(以下、現中計)では、「SOC Vision2035」の第1ステップとして「既存事業収益改善」と「成長基盤構築」を戦略の軸として取り組んでいます。セメント事業では販売価格の値上げを実施し、新材料事業では静電チャック(以下、ESC)需要の回復も見込まれています。現中計の最終年度である2025年度は、連結売上高2,650億円、営業利益214億円、ROE8.0%以上、ROIC5.0%以上という目標の達成が現時点では難しいと見込まれますが、セメント事業においては、お客様との値上げ交渉に粘り強く注力し早期の値上げ効果発現と、カーボンニュートラル投資の成果を最大限に発揮し、最後の一歩までやりきる覚悟です。
また、今後の販売拡大に対応する為にESCの新製造棟建設など、2026–28年度中期経営計画(以下、次期中計)の土台となる施策も進行しており、2035年度にセメント事業とそれ以外の事業の売上高比率を50:50とし、連結売上高を4,000億円、営業利益400億円以上に拡大するという事業ポートフォリオの変革に向けた基盤は着実に整ってきています。
「SOC Vision2035」の実現へ第2ステップへの挑戦
「SOC Vision2035」実現に向けた第2ステップとなる次期中計では、「事業ポートフォリオ変革推進」をスローガンにセメント事業の収益安定化を基盤に、成長分野の拡大と、研究成果の事業化に向けた準備を通じて、ポートフォリオ変革に踏み込む段階だと考えています。
特に、CO2再資源化人工石灰石を中心とする「カーボンビジネス」は、サステナビリティ推進部とセメント・コンクリート研究所が中心となり、現中計期間中に種まきを行い、その芽が少しずつ出てきました。今後はその事業化に向け、営業各部門と工場が一体となって全社的な取り組みを本格化させていきます。
更に、海外セメント事業として豪州事業の更なる拡大と新たな海外事業の展開、環境(廃棄物・副産物の再資源化)、建材分野においても新規事業の発掘に注力します。その為に、若手にも積極的にアイデアを出して欲しいと思いますし、上司のバックアップも重要ですので、それができるような企業風土づくりを行っています。
株主還元については、2025年5月発表の業績見通しにおいて、2025年度の自己株式取得を含めると、現中計期間中の総還元性向が3ヵ年平均で57%となり、同じく50%以上とした目標を達成する見込みです。次期中計における株主還元方針は、利益水準や投資計画を踏まえて慎重に検討してまいります。
2050年カーボンニュートラルに向けた技術革新への挑戦「SOCN2050」
2020年に打ち出した当社グループのカーボンニュートラルへの道筋となるビジョン「SOCN2050」では2030年までに石炭を中心とした化石エネルギーの代替率を50%以上に引き上げる目標を掲げ、達成に向けた諸施策を着実に実行しています。一方で、2024年12月に政府から発表された新たな排出量削減目標(NDC)や、2026年度から導入される排出量取引制度(GX-ETS)など、策定から4年以上が経過し、外部環境が大きく変化している為、ビジョンの見直しも進めています。次期中計の策定において、今後のカーボンニュートラル投資の計画を精査し、反映させていきます。
セメント産業は、主原料である石灰石の脱炭酸反応から発生するプロセス起源のCO₂排出が約60%を占め、排出量削減困難業種と呼ばれています。だからこそ、私は、この課題に正面から取り組むことこそが「環境解決企業」を掲げる当社の使命であると捉えています。
プロセス起源CO2排出量削減に向けて、CCU(CarbonCapture and Utilization)で少しでもCO2を利活用したいと考え、NEDOグリーンイノベーション基金採択事業の炭酸塩生成の研究成果であるCO2再資源化人工石灰石の製造試験と、そのさまざまな用途への利活用の研究開発に取り組んでいます。2025年4月には、既存の製造試験設備(大阪市大正区)から能力を10倍に引き上げた年間生産能力270tの製造試験設備を栃木工場(栃木県佐野市)内に建設しました。また、他産業との連携により、CO2再資源化人工石灰石が多様な製品分野で活用できることが見えてきています。
加えて、セメント製造におけるCO2排出の大部分はクリンカ(中間製品)を焼成する工程において発生する為、セメント中のクリンカ比率を引き下げ、ほかの材料に置換することは、有効な排出量削減手段の一つです。一般社団法人セメント協会を中心に働きかけたJIS改正では、普通ポルトランドセメント中の石灰石をはじめとした少量混合成分の上限比率を5%から10%へ引き上げる改正に合わせた規格が2025年度中に制定される見通しです。当社もそれに対応した生産体制の構築を進めていきます。また、国土交通省の各地方整備局ではスラグ等を55%以上使用した低炭素コンクリートブロック活用工事が推進されており、今後もこうした動きは更に加速すると考えています。混合セメントの生産体制の強化について検討を進めています。
更に、CCS(Carbon Capture and Storage)などの革新技術も含め、脱炭素への多様なアプローチの追求と、多様なCCU施策による最適な削減ミックスを目指していきます。
グループ会社との連携と一体経営
グループ全体でビジョンを実現するには、グループ会社それぞれが成長し、役割を果たしていくことが不可欠です。これまでも着実に成果を上げてきた各社ですが、今後はより高い成長目標に向けて一丸となって取り組んでまいります。
グループ経営の一体化を進める上では、ガバナンス体制の整備と、各社の自主性の尊重を両立させることが重要です。共通の経営理念のもと、それぞれの強みを活かしながら、柔軟でスピード感のある経営を支援していきます。
人と組織の進化が未来をつくる
ビジョンを実現する上で最も重要な資産は「人財」です。社員成長の為の投資や給与水準の引き上げを継続的に行っていますが、「チェンジ&チャレンジ」「チームワーク」「プロフェッショナル」という3つのキーワードで、社員一人ひとりの成長が、企業の成長と直結するという信念のもと、人事制度の改革や育成の仕組みの強化、外部人財の登用、自律的な人財の拡大など、組織全体の変革を進めています。
2024年に実施した従業員エンゲージメント調査で浮かび上がった課題を踏まえ、社員が安心して能力を十分に発揮できるよう人事制度の改定を進めています。また、人事評価についても能動的に考え動くことを積極的に評価する仕組みに変えていきます。
ガバナンス強化ー変革を支える「骨格」
変革し続けるには、強固なガバナンスが不可欠です。2024年から指名・報酬委員会における議論を重ね、取締役のスキル・マトリックスにおいて新たに「SOCVision2035」や中期経営計画、「SOCN2050」の実現に必要な取締役会のスキルを再定義し、明確化しました。各取締役が改めて自身の使命を再認識するとともに、今後の後継者計画は、これも踏まえて人選を考えていきます。加えて、業績や中長期の成長への貢献が報酬に反映されやすいように役員報酬制度の改定も行い、取締役が当社グループの成長に向けて更にコミットする体制を作りました。
更に、全ての取締役と監査役を対象に実施した取締役会の実効性評価において、高機能品事業に精通した有識者との連携を強化していく必要性が課題として挙がりました。外部の有識者から助言や意見を得ることは、スピードの速い市場環境の変化に対応し、競争に打ち勝つ一助になるものと考え、その充実を図ってまいります。また、社外取締役や女性役員の増加が求められていますが、将来に向けた検討は今後も継続していきます。
ステークホルダーの皆様へー変革の先に未来を
2025年度は現中計の最終年度であり、次期中計への移行に向けた重要な節目の年です。まずは、現中計で掲げる目標に向けて利益の上積みを図り、次期中計への弾みをつけます。そして、次期中計では「事業ポートフォリオ変革推進」を着実に実行できるようSOCグループ社員全員が自分事として共有できる目標と実行計画を策定していきます。
「成果は、自己の描いた理想に比例する」と言います。熱い思いが強ければ、強いほど目標は達成できると私は考えています。国内セメント需要の縮小、脱炭素化の加速、高度情報化といった環境変化は続きますが、軌道修正をかけながら「SOC Vision2035」という最終到達点に向かってグループ一丸となって突き進んでいきます。
今後とも、皆様の変わらぬご支援とご期待を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。